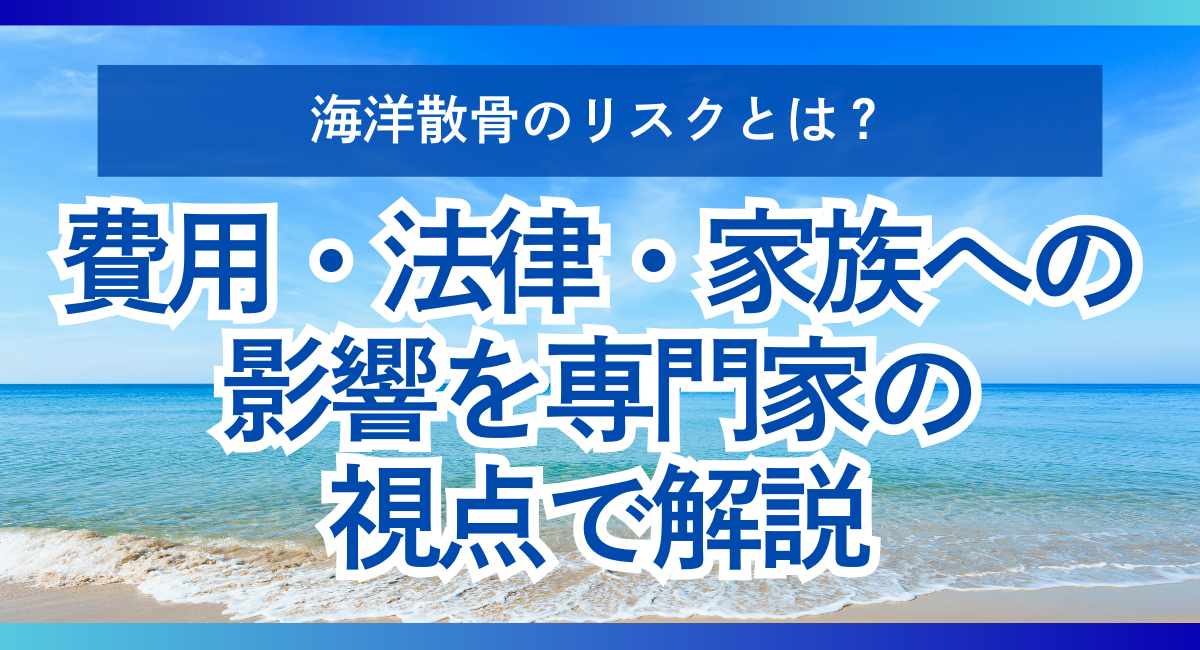近年、故人の希望や自然志向のライフスタイルから、海洋散骨を選ぶ方が増えています。華やかな葬儀やお墓の管理が不要になる一方で、実は、費用面や法律上の手続き、家族への心理的な影響など、事前に知っておくべきデメリットも存在します。
特に、相続や家計の観点から見た場合、散骨に伴う費用やトラブルの可能性を正しく理解しておくことは、家族全員の安心につながるでしょう。今回の記事では、FPの視点から「海洋散骨の費用」「法律上の注意点」「家族への影響」を整理し、後悔のない選択をするためのポイントを解説します。

海洋散骨とはどのような供養方法なのか?

海洋散骨とは、遺骨を粉骨にして海に撒く自然葬の一種です。従来の墓地に遺骨を安置する方法と比べて、管理費がかからず、自然志向の葬送方法として、近年注目を集めています。「家族に経済的・精神的な負担をかけたくない」「自然に還りたい」という理由で、選ばれるケースが多いです。このような背景には、墓地の維持管理費の高騰や、都市部での墓地不足、ライフスタイルの多様化といった社会的要因も影響しています。
しかし、海洋散骨にはメリットだけでなく、知っておくべきデメリットや注意点もあります。まず、法的には海洋散骨を直接禁止・規制する法律は日本には存在しません。厚生労働省や専門団体が示すガイドラインに従い、遺骨を小さなパウダー状にします。陸地から一定距離以上離れた海域で、節度を持って行うことが原則とされます。

しかし、各自治体によっては独自の規制があり、海洋散骨の実施場所や方法に注意しなければなりません。また、粉骨処理を怠ったり、遺骨をそのままの形で撒くと、法的な問題や家族間のトラブルになる可能性があります。
海洋散骨は、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点でも注目される葬送方法です。一般的な墓地に比べて、費用が大幅に抑えられるため、家族の経済的な負担を軽減できる点が大きなメリットです。一方で、墓地のように遺骨を納める「場所」が残らないため、家族が故人を追想する場所を持てないというデメリットもあります。海洋散骨は、近年増えている自然葬の一つですが、家族全員が納得したうえで実施することが、後悔のない選択につながります。
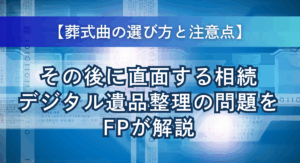
散骨の種類と特徴を解説

海洋散骨には、さまざまな方法があり、家族のニーズや予算、参加可能な人数などに合わせて選べます。複数の遺骨をまとめてまく「合同散骨」や、家族だけで行うプライベートな「個別散骨」があります。
また、船上でセレモニーを兼ねてお別れの時間を過ごす「クルーズ散骨」も存在するのです。海洋散骨は、費用面や手間の面で大きな差があります。それぞれに特徴やメリットがあるため、どの方法が家族の想いに合うのかを理解して選びましょう。
| 海洋散骨の方法 | 費用の目安 | 特徴・メリット | 注意点・デメリット |
| 合同散骨 | 約10万〜20万円 | ・複数の家族で費用を分担できる ・費用を抑えられる | ・日時や場所の自由度が低い ・他の家族と一緒になる |
| 個別散骨 | 約15万〜35万円 | ・船を貸し切り、家族や親しい人だけで実施できる ・日時や場所を自由に決めやすい | ・費用は合同散骨より高めになる ・人数や船の規模で費用が変動する |
| クルーズ散骨 | 30万円以上 | ・セレモニーも兼ねて、特別な時間を過ごせる ・プライベート感が強い | ・費用が高めになることが多い |
【個別散骨】故人一人だけを海に還す方法

個別散骨の大きな魅力は、故人だけの特別な供養ができることです。他の遺骨と混ざらず、家族の希望に合わせて、日時や場所を選べます。小規模で落ち着いた雰囲気で故人を追想できるため、多くの家族にとっても安心できる要素です。
一方で、個別散骨には注意点もあります。専用の船を手配して行うため、日程調整や準備に手間がかかる場合があります。参加人数や選ぶプランによっては、費用が膨らむかもしれません。
法的に特別な許可は不要ですが、散骨には、さまざまなルールが存在します。遺骨は、必ず1〜2mm程度に粉骨しなければなりません。自治体の条例や海域のルール、自然環境への配慮を守る必要があります。
粉骨をきちんと行わなければ、法律違反になる可能性もあるため、多くの家庭では専門業者に依頼するのがおすすめです。個別散骨は、故人の意思や家族の想いを尊重しやすい方法です。一方で、費用や準備の手間、法律やマナーを守る慎重さが求められます。
| 個別散骨について | 内容 |
| メリット | ・故人だけの特別な供養が可能 ・他の遺骨と混ざらない ・日時や場所を自由に選べる ・小規模で落ち着いた雰囲気で実施できる |
| 注意点 | ・専用の船を利用するため、日程調整や準備の手間がかかる ・参加人数やプランによっては、費用が高くなる |
| 法的ルール・マナー | ・特別な許可は不要 ・遺骨は1〜2mm程度に粉骨する必要がある ・自治体の条例や海域のルールを、遵守しなければならない ・漁業や交通の妨げになる場所は避ける |
| 粉骨の扱い | ・適切に行わないと法律違反の可能性がある ・専門業者に依頼してトラブルを回避することがおすすめ |
【合同散骨】複数の遺骨を一緒に海に還す方法

合同散骨のメリットとして、まず挙げられるのは、費用が安価で済む点です。複数の遺骨をまとめて散骨するため、船や散骨業者の手配が効率的に行えます。個別散骨に比べて、費用負担が大きく軽減されるのです。一般的に合同散骨の費用相場は10万円から20万円程度になります。複数の故人と一緒に供養することで、穏やかで温かな雰囲気を作りやすく、心の支えや励みにつながることもあります。
一方で、合同散骨の注意点も理解しなければなりません。まず、故人だけを特別に散骨するのは難しいです。遺骨が他の方と混ざるため、個別の供養を重視したい場合には、物足りなさを感じることがあります。また、散骨の際に、業者のプランや散骨海域のルールに従わなければならず、散骨日時や場所の自由度は制限されます。
多くの業者では、合同乗船の場合、散骨に参加できる人数も2〜3名程度に制限されることが多く、すべての親族が参加できるとは限りません。静かでプライベートな空間にならない可能性もあります。

| 合同散骨について | 内容 |
| メリット | ・費用が安価(相場10万〜20万円程度) ・船や業者の手配を効率的に行える ・個別散骨に比べて、費用負担が軽い ・複数の故人を一緒に供養することで、穏やかな雰囲気を得られる |
| 注意点 | ・他の遺骨と混ざってしまう ・個別供養を重視する人には、物足りない可能性がある ・日時や場所の自由度が低く、業者や海域のルールに従わなければならない |
| 参加人数の制限 | ・合同乗船では、2〜3名程度しか参加できないことが多い ・すべての親族が参加できない場合がある ・プライベート感が薄れる可能性がある |
【両立させる選択肢】手元供養と一緒に行う散骨方法

個別散骨や合同散骨のほかに「手元供養」と、組み合わせることもできます。手元供養とは、故人の一部の遺骨を自宅で保管したり、小さな骨壺やアクセサリーに入れたりして、日常的に供養する方法です。より身近に故人を感じられる、新しい供養スタイルとして注目されています。
散骨と手元供養を組み合わせると、海や山などの自然に広く遺骨を還す散骨の供養と、自宅でいつでも手を合わせられる手元供養の両方を、実現できるのが大きなメリットです。遠方に住む家族や忙しい家族も、いつでも故人に思いを馳せる環境が整います。
また、合同散骨と手元供養を組み合わせると、散骨の費用や手間を抑えながらも、一部の遺骨を自宅で大切に供養できるため、経済的な負担も軽減できるでしょう。制約がある合同散骨の場合でも、自宅での手元供養があることで、故人との心のつながりを感じやすくなります。
| 両立の選択肢 | 内容 |
| 手元供養について | ・故人の一部の遺骨を自宅で保管する供養方法 ・小さな骨壺やアクセサリーに収めることも可能 ・日常的に故人を身近に感じられる新しいスタイル |
| 「散骨+手元供養」のメリット | ・自然に還す散骨と、自宅での供養を両立できる ・遠方に住む家族や忙しい家族も、いつでも故人を偲べる |
| 「合同散骨+手元供養」のメリット | ・合同散骨によって費用や手間を抑えつつ、一部の遺骨を自宅で供養が可能 ・合同散骨の制約(日時・場所・プライベート感の不足)を補える ・経済的な負担を軽減しつつ、心のつながりを保てる |
海洋散骨の法的手続きのポイントと注意点

先述でも簡単に触れましたが、散骨は自由に行えるわけではありません。たとえば、海上で散骨をする場合、自治体によっては、事前の許可が必要です。また「港から一定の距離以上離れた場所で、散骨しなければならない」といった決まりもあります。
これは、漁業権の保護や海の環境を守るために設けられているのです。このようなルールを無視して散骨を行うと、地域住民とのトラブルが生じることもあります。日本全国で散骨を禁止する法律はありません。しかし、地域ごとに条例で散骨を制限・禁止している場所もあります。たとえば、北海道の長沼町や長野県の諏訪市では、厳しい規制が存在します。
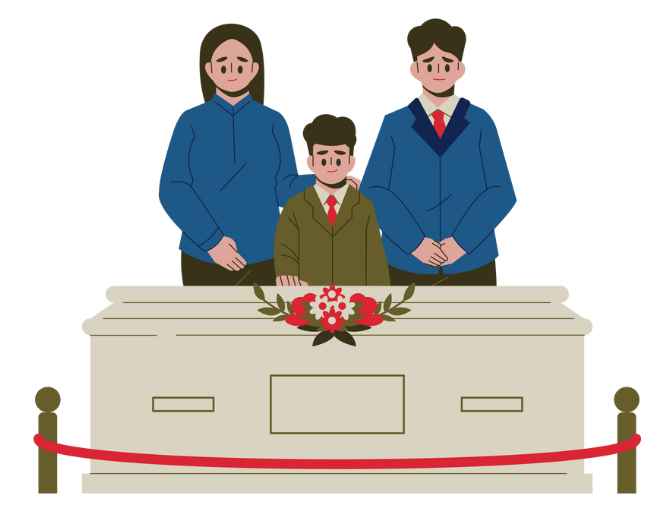
また、海洋散骨において、遺骨を細かく砕いてから散骨することが重要です。粉骨しないまま散骨すると、刑法の死体遺棄罪に触れる可能性があります。専門の業者に粉骨を依頼することが一般的です。
ファイナンシャルプランナー(FP)の視点では、法的な手続きを無視して散骨を行うことは、将来的に家族間のトラブルや罰則リスクにつながる危険性が高いと考えます。違法な散骨が発覚すると、罰金や行政指導の対象になります。
散骨を検討している家族は、必ず自治体や信頼できる専門業者に確認して、許可や規制の状況を把握してから、準備を進めましょう。経験豊富な業者に依頼すれば、許可申請や適切な手続きを代行してくれるため、安心して散骨ができます。散骨は、一見自由な供養方法のように思えますが、実際には、法的な規制や地域ごとのルールが存在するため、正しい知識と準備が不可欠です。
相続や散骨が家族に及ぼす心の影響

墓がないために、遺骨を手元に残したい家族にとって、散骨は「少し物足りない」と感じることがあります。散骨の場合、家族がその場に立ち会ったり、後から直接お参りしたりすることが難しいためです。高齢の親族や移動手段が限られている家族にとっては、故人を身近に感じにくく、心理的な寂しさや喪失感が強くなることもあります。
このような心理的な負担は、単なる気持ちの問題にとどまらず、家族全体の関係性にも影響します。供養のあり方に対する価値観の違いから意見の対立が起こり、場合によっては、親族同士の協力体制が崩れてしまうこともあるのです。その結果、遺骨の扱いについて、トラブルに発展するリスクも考えられます。
不安や対立を避けるには、事前に家族全員で散骨の意義や方法について話し合い、理解を共有しておくことが大切です。不安や疑問を解消する時間を持つことで、お互いの思いを尊重しながら、納得のいく形で供養できます。必要に応じて、専門家や僧侶に相談するのも有効です。散骨は「心の距離」を生みやすい供養方法だからこそ、家族の気持ちに寄り添い、丁寧にコミュニケーションを重ねることが、円満な供養につながります。
海洋散骨のお金の面で気をつけたいこと

海洋散骨は、一見するとお墓を建てるより費用が安いように思えますが、実際にはさまざまな費用がかかるでしょう。船を借りる費用、遺骨を細かく砕く粉骨費用、散骨に関する手続き代行費用などが挙げられます。これらが重なることで、想像以上に出費が増えることもあります。
たとえば「個別散骨」は、船をまるごと貸し切るため、費用が高くなりやすいです。場合によっては、50万円前後になる可能性もあります。日時や場所を自由に選べるメリットがある反面、高額になりやすい点には、注意しなければなりません。これに対して「合同散骨」は、複数の家族で費用を分担できるため、経済的な魅力があります。

ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から大切なのは「費用・内容・信頼性」を総合的に比較することです。安さだけではなく、サービスにどこまで含まれているか、業者の信頼性を確認しましょう。複数の業者から見積もりを取り、必要なサービスが網羅されているかをチェックするのがおすすめです。
また、散骨は一度きりの儀式になります。単なる費用比較に終わらず、家族にとっての満足度や心の区切りも、重視して選ぶことが大切です。散骨を検討する際は「経済的負担」と「家族の心の満足感」のバランスを取りながら、納得できるプランを話し合いましょう。
| 費用について | 内容 |
| 主な項目 | ・船のチャーター費用 ・遺骨を粉末化する粉骨費用 ・散骨手続きの代行費用 |
| 個別散骨 | ・船を一艘貸し切るため費用が高い ・相場:20万〜50万円程度 ・日時や場所を自由に選べる ・セレモニー内容を充実させやすい |
| 合同散骨 | ・複数家族で費用を分担でき経済的 ・相場:10万〜20万円程度 ・日時や場所の自由度は低め |
| FP視点での注意点 | ・費用だけでなく「内容・信頼性」を比較することが重要 ・複数の業者から見積もりを取る ・サービス内容に必要な項目が含まれているか要確認 |
| 供養としての考慮点 | ・散骨は一度きりの儀式であり「費用」と「家族の心の満足感」の両立が重要 ・高額な個別散骨は丁寧で自由度の高い供養が可能 ・合同散骨は経済的で負担を抑えやすい |
天候や自然の変化がもたらす影響

海洋散骨は海の上で行うため、天候や海の状況に大きく影響を受けます。強風や高波、台風の接近などの悪天候時には、散骨が延期や中止になるケースがあります。計画していた日程通りに、散骨が実施できないかもしれません。そのような可能性があることを事前に理解しておく必要があります。散骨が延期となった場合、再調整や再予約が必要になります。家族や関係者のスケジュール調整も、影響を受けることが多いです。
また、散骨の実施可否は通常、散骨直前の天候や海況をもとに、船長や散骨業者が判断します。散骨の日程が確定するのは、数日前になることが多いです。家族が遠方から集まる場合は、このような不確定要素を、あらかじめ理解しなければなりません。連絡手段を確保しておくことが安心へとつながります。

さらに、天候による延期や中止のリスクを減らすため、散骨に適した季節や海域を選ぶことも検討のポイントです。一般的には、春や秋の穏やかな気候の時期が散骨に向いており、台風シーズンや冬の荒れやすい海は避けたほうが安心です。海洋散骨を計画する際には、天候リスクを十分に考慮して、余裕のあるスケジュール管理を行ってください。家族の精神的・経済的な負担を軽減するうえで、重要なテーマになります。
| 項目 | 内容 |
| 天候の影響 | ・強風・高波・台風接近などで延期や中止の可能性あり ・予定通りの実施ができない場合がある |
| 延期時の対応 | ・日程の再調整・再予約が必要 ・家族や関係者のスケジュールに影響大 |
| 判断基準 | ・実施可否は船長や散骨業者が直前の天候・海況で判断 ・確定は数日前になるケースが多い |
| 遠方の家族への影響 | ・不確定要素があるため、事前の理解が必要 ・連絡手段をしっかり確保しておくことが安心につながる |
| リスク低減の工夫 | ・春や秋など穏やかな季節を選ぶ ・台風シーズンや冬の荒天期は避ける |
海洋散骨と樹木葬の違いを紹介

合同散骨や樹木葬などの自然葬には、さまざまな形がありますが、特に海洋散骨は「自然に還る」という象徴性が強いため、多くの方に選ばれています。樹木葬は、墓地内の特定の区画に遺骨を埋葬して、樹木や草花を墓標とする方法です。
故人の場所が、明確に残る点が特徴になります。定期的にお参りしたい方には安心感がありますが、個別区画を持つ場合は、散骨より費用が高くなることが多く、管理費用も必要です。その点、海洋散骨は「広大な自然に還す」という、自由で開放的なイメージが強いです。
先述のように、手元供養やメモリアルグッズを併用すれば、散骨で場所が特定できない不安を補えます。海洋散骨や樹木葬などの自然葬には、それぞれメリット・デメリットがあります。故人の意思や家族の生活環境に合った方法を選ぶことが、後悔のない供養につながるでしょう。
| 供養方法 | 特徴・イメージ | メリット | デメリット・注意点 |
| 海洋散骨 | ・遺骨を海にまき「自然に還る」象徴性が強い ・自由で開放的なイメージ | ・費用が比較的安い ・自然と一体化する自由な供養が可能 | ・遺骨の場所を特定できない ・定期的なお参りが難しい |
| 樹木葬 | ・墓地内の区画に遺骨を埋葬 ・樹木や草花を墓標とする | ・故人の場所が明確に残り、安心感がある ・定期的なお参りが可能 | ・散骨に比べ費用が高い場合が多い ・管理費が必要 |
海洋散骨とデジタル遺品が現代で重要になっている

近年、故人の遺骨を海洋散骨で供養するケースが増えています。しかし、散骨を選ぶと「形ある遺骨」が手元に残りません。家族が供養の拠り所を感じにくくなることがあります。このような背景から、デジタル上に残る記録や資産が、家族にとって新たな「供養の場」や「相続確認の材料」として重要になっているのです。
たとえば、故人が利用していたSNSアカウントや電子メール、ネット銀行や暗号資産などのデジタル遺品は、手元に遺骨がなくても、家族が故人を偲ぶきっかけになります。資産整理の根拠にもなるのです。しかし、パスワードやアクセス方法がわからなければ、家族だけで対応するのは難しい場合もあります。
このような場面で、活躍するのがデジタル遺品業者です。専門家によるサポートにより、故人のデジタル遺品の整理・確認・相続手続きがスムーズに進められます。また、必要に応じて、故人のデジタルコンテンツを家族が閲覧できる形に整えることで、散骨後も心の拠り所を残すことが可能です。海洋散骨を選ぶ際は、単に遺骨の処分だけでなく、デジタル遺品の整理・活用も視野に入れることで、家族の安心感と供養の質を高められます。
デジタル遺品整理との共通点と関係性
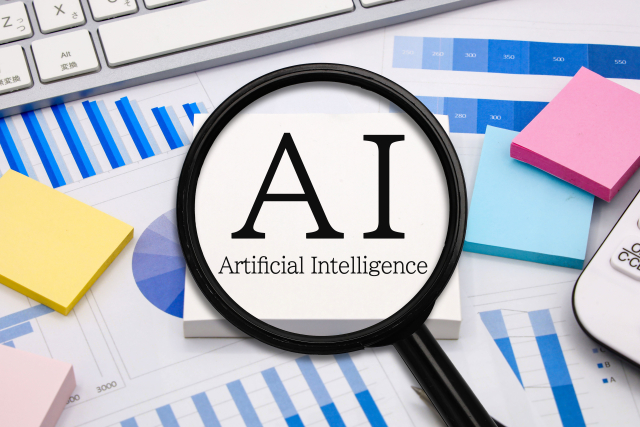
海洋散骨とデジタル遺品整理は、一見するとまったく別の領域に思えます。しかし「現代ならではの供養・遺産整理」という共通した特徴を持つのです。
まず、海洋散骨とデジタル遺品に共通するのは「形のないものを整理する」という点です。海洋散骨は、遺骨を海に還すことで物理的な形を残さず、自然の循環で供養します。一方で、デジタル遺品は写真やメール、SNSやオンライン口座など、目に見えないデータという「形なき資産」を扱います。どちらも目の前に残る実体がないため、家族にとって整理の仕方が重要です。

また、双方に通じるのは「事前準備の必要性」です。故人が散骨を望んでいたのか、家族が供養に納得できているのかを、明確にしておく必要があります。デジタル遺品に関しても、パスワードや契約内容を生前に共有していなければ、資産にアクセスできません。
「専門家の力が安心につながる」という点も共通しています。海洋散骨では、海域ごとの条例や環境保全の配慮、遺骨の粉骨が必要です。法律的・実務的な知識が欠かせません。デジタル遺品でも、データの安全な取り扱いや、相続税の複雑な問題が絡み合います。
専門家の助けが大きな支えになるでしょう。専門家によるサポートがあることで、家族は「正しく」「安心して」整理を進めることができるのです。
| 共通テーマ | 海洋散骨の特徴 | デジタル遺品整理の特徴 |
| 形のないものを整理する | 遺骨を海に還して、物理的な形を残さない供養方法 | 写真・メール・SNS・口座など「目に見えないデータ資産」を扱う |
| 事前準備の必要性 | ・故人が本当に散骨を望んでいたか明確にする必要がある ・家族が納得していなければ、迷いやトラブルにつながる | ・ログイン情報や契約内容を共有しなければ、資産にアクセスできない ・準備不足は、家族の混乱を招く |
| 専門家の力で安心 | ・条例や環境ルールに従う ・遺骨の粉骨処理など、法律的・実務的な知識が必要になる | ・データの安全な扱いが必要になる ・相続や課税など、法律面で複雑な問題がある |
| 家族の安心につながる効果 | 専門家が関わることで「正しく、安心して」供養が行える | 専門家のサポートにより、混乱を避け、安心して整理できる |
海洋散骨とデジタル遺品の終活に取り入れるポイント

家族が行う海洋散骨において、前提に、故人が生前にどのような葬儀を求めているのかを、話し合う必要があります。終活の中で大切なのは、亡くなった後に家族ができるだけ迷わず、安心して対応できるよう準備することです。ファイナンシャルプランナー(FP)の具体的なポイントとして「エンディングノート」や「遺言書」が挙げられます。自身の希望を明確に残すことが大切です。
たとえば「海洋散骨を望むのか」「樹木葬にしたいのか」といった供養の形を伝えましょう。どの業者に依頼したいのか、費用をどのように準備するのかを記載しておくと、残された家族は判断に迷いません。また、近年では、写真データやSNSアカウント、ネット銀行など、多くの「デジタル遺品」が個人に残るようになっています。
これらは放置すると解約できなかったり、管理が難しくなったりするため、一覧を作成してください。管理方法やパスワードの引き継ぎ方法を、記しておくことが重要です。

散骨やデジタル遺品の対応を行う業者に、生前のうちから、相談するのもおすすめです。業者のサービス内容や費用を確認して、希望に合った方法を決めておくことで、家族にとって、大きな負担軽減につながります。散骨は、天候や日程の調整が必要であり、デジタル遺品は、セキュリティや法的な問題が絡みます。そのため、専門家と一緒に準備を進めておくと安心です。
本人の希望が明確であればあるほど、家族同士の意見の食い違いが減り、心理的な負担も少なくなるでしょう。終活の準備は、単なる「自身の希望を叶えるため」だけではありません。家族の「安心や心の安定を守るため」にあるのです。
| 故人が亡くなる前に行える内容 | FP視点での論点・具体的ポイント |
| 前提条件 | ・生前に「希望する葬送方法(例:海洋散骨・樹木葬・納骨堂)」を家族と共有しておくことが不可欠 ・不明瞭な場合、相続開始後に家族間の対立やトラブル要因となる |
| 記録方法 | ・エンディングノートや遺言書に具体的に明示する ・希望だけでなく、必要な費用の準備計画・支払い方法(生命保険の死亡給付金、預貯金、相続財産からの充当)をセットで記載する ・依頼業者名、サービス概要を記録して、意思決定の透明性を確保しておく |
| デジタル遺品への対応 | ・写真・動画・SNS・サブスクリプション契約・ネット口座などを、資産リスト化する ・パスワード管理方法を提示する(パスワードマネージャー利用、セキュリティレベルを保持した引き継ぎ) ・未整理の場合、金融資産の喪失リスクや、課金トラブルが発生する懸念がある |
| 専門業者との事前相談 | ・散骨は天候・日程調整のリスクがあるため、複数日程候補やキャンセル規定を確認する ・法的要素が絡むため、専門業者の関与が望ましい |
| リスクマネジメント | ・散骨遅延・中止に伴う追加費用、遠方から参列する家族の負担を想定する必要がある ・デジタル遺品放置による情報漏洩・経済的損失への備えが欠かせない |
| 効果・価値 | ・本人の意向明示により、家族間トラブル・心理的負担を回避できる ・財産管理・供養方針の「見える化」によって、家族の安心と、円満な遺産承継を実現できる |
まとめ

海洋散骨は、自然に還る供養方法として魅力的にみえます。一方で、法的なルールや粉骨の必要性、供養の場所、費用、天候リスクなど、さまざまな注意点も把握しなければなりません。デジタル遺品整理に関しても、SNSアカウントやネット銀行、クラウド上のデータといった「形のない遺産」をどのように扱うかが、課題となります。

供養や遺産整理を考える際には、散骨の細かい内容や、デジタル資産の扱いを事前に整理しましょう。専門業者のサポートを受けながら、準備を進めることで、家族全員が納得できる形を選択できます。海洋散骨とデジタル遺品整理は、どちらも現代ならではの「新しい供養と遺産整理の形」です。故人の終活としても、なるべく早めに対策しなければならないテーマです。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,000件以上の記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、不動産、保険、相続分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
【デジタル資産バトン(デジタル遺品調査サービス)のご案内】
「故人が遺したPCやスマートフォンのパスワードが分からず、開けない」 「ネット銀行や仮想通貨を保有していたはずだが、情報が見つからない」 「どのようなデジタル資産があるか分からず、相続手続きが進められない」
ご家族が亡くなられた後の、デジタル遺品の整理でお困りではありませんか。 「デジタル資産バトン」は、ご遺族に代わって故人のPCやスマートフォンなどを調査し、相続に必要なデジタル資産の情報を見つけ出すサービスです。
私たちは、ご遺族のお気持ちに寄り添い、以下の内容で信頼性の高い調査をお約束します。
✔️ PC・スマートフォンのデータ調査 ロック解除やパスワード解析を行い、アクセスできなくなった故人のデジタル機器を調査します。専門技術で内部のデータを抽出し、資産や契約の手がかりを探します。
✔️ デジタル資産の発見サポート 調査で得られた情報をもとに、ネット銀行、証券口座、暗号資産(仮想通貨)、各種サービスの契約など、ご遺族が把握していなかった資産や契約の発見をサポートします。
✔️ 相続手続きのための報告書作成 発見された資産や契約に関する情報を整理し、相続手続きに利用しやすい形で報告書としてお渡しします。
✔️ 徹底した秘密保持 故人のプライバシーと、ご遺族からお預かりする情報を厳格に管理し、秘密を守ります。安心してご依頼いただける体制を整えています。
✔️ 専門家との連携 調査結果をもとに、弁護士や税理士など相続の専門家へのご相談が必要な場合も、スムーズな連携が可能です。
故人の大切な資産を、確実な形で未来へつなぐために。 まずはお困りの状況を、専門の担当者へお聞かせください。
▼ 詳細・ご相談はこちらから ▼